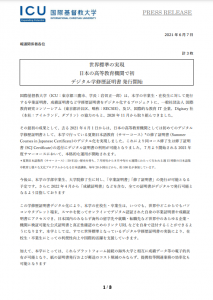SIIEJ2026 開催のご案内
Announcement of SIIEJ 2026
国際教育夏季研究大会(SIIEJ)2026は、
2026年8月5日(水)・6日(木)に、桜美林大学 新宿キャンパスにて開催予定です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
ぜひ大会日程をカレンダーにご登録のうえ、ご予定ください。
Save the Date:2026年8月5日(水)・6日(木)
The Summer Institute on International Education (SIIEJ) 2026
is scheduled to be held on August 5 (Wednesday) and 6 (Thursday), 2026, at J. F. Oberlin University.
We warmly welcome your participation.
Save the Date : August 5–6, 2026
________________________________________
<日時(Date)>
2026年8月5日(水)-6日(木)
August 5 (Wednesday) – August 6 (Thursday), 2026
________________________________________
<会場 (Venue)>
桜美林大学 新宿キャンパス
〒169-0073 東京都新宿区百人町3丁目23-1
JR新大久保駅(JR山手線)より徒歩8分、JR大久保駅(JR中央・総武線)北口より徒歩6分
J. F. Oberlin University, Shinjuku Campus
3-23-1 Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073, Japan
8-minute walk from JR Shin-Okubo Station (JR Yamanote Line)
6-minute walk from the North Exit of JR Okubo Station (JR Chuo Line, Sobu Line)
________________________________________
<大会テーマ(Conference Theme)>
オールジャパンの国際教育プラットフォーム構築を目指して
Towards the Creation of an All-Japan Platform for International Education
________________________________________
<概要(Overview)>
SIIEJ(国際教育夏季研究大会)は、国際教育にかかわるすべての人々が、所属機関や職種を超えて相互に学びあう場として発展してきました。2026年のSIIEJは「 オールジャパンの国際教育プラットフォーム構築を目指して 」をテーマとして、桜美林大学新宿キャンパス(東京都新宿区)で開催されます。展開期を迎える国際教育の環境分析、国際共修、オンラインを駆使したCOIL型教育交流、留学生のリクルートとデジタル・マーケティングなど、国際教育にかかわるワークショップやセッションを実施いたします。昨年の大会(京都先端科学大学)では、過去最高の371名の会場参加、133名の方にオンライン参加いただきました。今年もより多くの国際教育関係者が相互に学びあう場としていきたいと思いますので、ご参集ください。
The SIIEJ (Summer Institute on International Education, Japan) has developed as a platform where individuals involved in international education can learn from one another beyond institutional and professional boundaries. The 2026 SIIEJ will be held at J. F. Oberlin University in Shinjuku, Tokyo under the theme, “Towards the Creation of an All-Japan Platform for International Education.” We will offer workshops and sessions covering topics such as analyzing the evolving international education landscape, COIL-based educational exchange programs, and international student recruitment and digital marketing. Last year’s conference, held at Kyoto University of Advanced Science (KUAS), had a record number of attendees with 371 participants on-site and 133 joining online. We aim to make this year’s event an even greater opportunity for international education professionals to learn from each other. We look forward to your participation.
________________________________________
大会セッションおよびワークショップの公募は2026年3月上旬より開始予定です。
また、参加申し込みは2026年5月下旬より受付開始予定です。
最新情報は、以下のウェブサイトにて随時更新いたします。
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/siiej2026
The call for session and workshop proposals is scheduled to open in early March 2026.
Conference registration is scheduled to open in late May 2026.
Further updates will be posted on the website below.
https://pub.confit.atlas.jp/en/event/siiej2026
________________________________________
過去大会のご報告(SIIEJのオフィシャルサイトに移動します)
2022年以前の大会のご報告はSIIEJのオフィシャルサイトにてご確認いただけます。